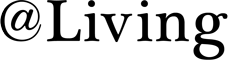仕事と家庭に対する価値観の多様化や経済的な事情などにより、仕事と育児を両立する世帯が一般的になっています。こうした社会の変化に合わせ、度々法改正されているのが、育児休業制度(以下、育休制度)です。
今年も4月と10月に法改正があり、育児に寄り添った働き方がより促進されます。産前産後休業制度(以下、産休制度)と育休制度について、これから制度を利用する人はもちろん、一緒に働く人も知っておきたいポイントを、社会保険労務士の櫻井純明先生にお聞きしました。
CONTENTS
産休・育休制度をおさらい!
2つの制度の違いとは?

まずは産休・育休制度がどのような法律に基づく制度なのか、教えていただきました。
「産休は、母体を守ることを目的に、労働基準法で定められた制度です。妊産婦さんのみが産前6週前から取得でき、産後8週間(医師の承認があれば産後6週間)は強制的に休まなければならないことが定められています。
対して育休は、仕事と育児の両立を支援する制度。少子化対策として、昨今、盛んに法改正が行われていて、女性だけでなく、パパになる男性や養親、特別養子縁組里親も取得できます」(社会保険労務士・櫻井純明先生、以下同)
産休、育休の制度概要をまとめると以下のようになります。
産休(産前産後休業)

・根拠法:労働基準法
・対象者:妊産婦
・期間:産前6週は自由に取得可能。産後8週は取得が義務付けられている
※出産日当日は産前扱いになる
※多胎妊娠(双子など)は14週前から取得が可能
※85日目以降の流産・人工妊娠中絶も出産扱いとなる
「産前休業をいつから取得するかは自由に決められます。出産日当日も産前に含まれるので、実際問題は別として法律上は出産日まで働くことができます。
反対に産後8週は、就労禁止が義務付けられています。ただし、産後6週間経過後に医師が認めた証明書がある場合は、職場復帰が可能です」
育休(育児休業)

・根拠法:育児・介護休業法(正式名称:育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
・対象者:子どもを養育する労働者。妻や夫のほか、子と養子縁組していれば、祖父母等も取得可能
・期間:出産予定日から原則子どもが1歳になるまで。事情があれば6カ月毎に2歳まで延長可能
※1歳までは2回に分割して取得できる(延長するときの育休は分割不可)
「育休は労働者のための制度。そのため会社役員などは対象外となります。ちなみに産休も労働基準法の制度のため、会社役員は適用外(産後8週間の就労禁止ルールも適用されません)となります。ただし、会社を通じて健康保険に加入していれば、会社役員も休業期間に対する出産手当金の支給(報酬支払日を除く)や社会保険料免除の措置を受けることは可能です」
育休は原則1歳になるまでとされていますが、保育所が見つからずに待機児童になった場合や、子育て中のパートナーの病気・離別によって自分が養育する必要が出た場合などは、6か月ごとに最長2歳まで延長できるそうです。
「企業によっては独自の制度を設け、3歳までや小学校入学前まで育休を取れるところもあります。とくに規模の大きい企業には、福利厚生として育児制度を整えているところが多いですね。ご自身の職場の制度もぜひ確認してみてください」
今年の制度改正で
より育児がしやすい世の中に
産休・育休制度は、2022年に大きく改正され、さらに今年(2025年)、4月と10月に新たな施策が加わります。それぞれどのような目的で改正が行われたのでしょうか。
「2022年には、4月と10月の2回に分けて大きな改正がありました。主な改正の目的は男性の育休取得率を上げること。仕事と育児を両立する女性の負担を減らすためにも、男性の育児参加は必要不可欠。男性が女性と同等まで育休取得率を高められるように環境を整え、安心して子育てできる世の中にするために制度改正が行われました」

主な改正内容は、(1)従業員に対する育休取得の意向確認義務化、(2)育休の分割取得制度、(3)産後パパ育休(出生時育児休業)制度の3つです。
「とくに(3)の産後パパ育休制度は、通常の育休とは別に男性が取得できる新制度。男性労働者(子どもが養子の場合は女性も取得可能)は、出産後8週間以内に4週間を上限に休業できます。通常の育休同様、2回に分割して取得することも可能です」
産後パパ育休は、通常の育休とは異なり、労使協定を締結しておけば、あらかじめ日時を申し出ることで休業期間中も就労できるのが特徴。夫婦で相談しながら上手に使っていきたい制度です。

では、2025年の法改正では何が変わるのでしょうか。
「今回の改正の目的は、3歳から小学生までの子育てをしやすくすることです。これまでの育休制度は生まれてすぐの育児を支援するものでしたが、今回、育休から復職した後も子育てをしやすいように改正されました。そのなかから主な3つの改正内容をご紹介します」
1.子の看護等休暇

「これまで、子どもの看病を目的に看護休暇を取得できるのは、子どもが小学校に就学する前まででした。しかし4月の改正により、対象期間が小学校3年生修了までに拡充。取得の理由も、看病だけでなく卒園式や入学式、予防接種、健康診断、感染症による学級閉鎖も対象になりました」
子どもが1人の場合は年5日、2人以上だと年10日の休業が可能となります。また、これまで入社6カ月未満の従業員は利用できない制度でしたが、今回の改正で入社6カ月未満でも利用できるようになりました。
「注意したいのは、制度では有給無給が定められていないこと。現状は、無給扱いとする会社が非常に多いです。その場合、年次有給休暇の残日数に余裕があるなら、そちらを優先するという選択肢もありえます」
2.所定外労働(残業)免除

「これは今までもあった制度ですが、免除対象が『3歳未満の子を養育する労働者』から、『小学校就学前の子を養育する労働者』へと広がりました。取得の1カ月前までに期間を指定することで、最低1カ月、最長1年、残業を免除できます。意外と知られていない制度なので、ぜひ多くの方に知っていただきたいです」
3.柔軟な働き方を実現するための措置

「これは10月から施行される制度になります。3歳以降、小学校就学前までの子どもを養育する労働者が対象で、柔軟な働き方を選択できるよう企業に義務付ける制度です。労働者を雇用していれば、個人事業主も含めすべての事業主が対象となります」
具体的には、企業が次の5つから2つ以上の制度を選び、就業規則等に定める必要があります。対象となる子育て中の従業員はそのなかから1つを選択でき、企業はそれを確実に実施しなければなりません。
【柔軟な働き方の5つの選択肢】
・時差出勤制度(1日の所定労働時間は変更しない)またはフレックスタイム制の導入
・テレワークの導入(1日の所定労働時間を変更せず、月10日以上利用できる)
・短時間勤務制度利用者の対象を3歳までから小学校就学前までに拡充
・養育両立支援休暇を別途年10日以上付与(有給か無給かは問わない)
・保育施設の設置運営、もしくはこれに準ずる便宜供与(ベビーシッター利用費の補助など)
「就業規則等にも関わる制度改正なので、企業の労務担当者はいろいろと大変かもしれませんが、子育て中の従業員にはうれしい制度ですよね。なおこの制度は、対象者に制度内容を周知するだけでなく、制度利用の意向を確認(聴取)することまで義務付けられています」
給付金にも改正あり!
産休・育休中にもらえる手当とは?

育児介護休業法とは別に、給付金に関わる改正も行われました。改正内容とともに、支給される給付金を確認しましょう。
産休中の給付 ※今回は改正なし
健康保険・厚生年金保険法により、以下の給付制度等が取り決められています。
出産手当金
出産前12カ月分の標準報酬月額平均額の2/3を産休した日数分支給
出産育児一時金
子ども1人につき50万円の一時金を支給
産休中の社会保険料免除
本人および事業主の社会保険料を免除
※期間は、産休開始日が属する月から、産休終了日の翌日が属する月の前月まで
育休中の給付金
休業期間中は雇用保険から以下の給付金が支給されます。
育児休業給付金
休業開始前6カ月分の賃金平均額の67%(上限あり)を当初180日間支給
181日目以降は、最長で1歳(延長の場合は最長2歳)の誕生日前々日まで50%を支給
休業を開始してから2カ月ごとに申請する必要あり
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
休業開始前6カ月分の賃金平均額の67%(上限あり)を支給
育休中の社会保険料免除
産休同様、本人・事業所ともに社会保険料を免除
免除期間は、育休開始日が属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで
「月末日1日だけの休業でもその月の保険料は免除になります。また、休業開始日と終了日が同じ月内にあり、月末日に休業していない場合も、合計して14日以上休業していれば免除となります。
さらに、賞与にかかる社会保険料は連続1カ月以上育休していないと免除されないなど、注意点がいくつかあるので、職場の担当者と相談しながら申請しましょう」

上記3点に加え、出産直後の夫婦協力子育て支援として、「出生後休業支援給付金制度」も4月よりスタートしました。
「これは、出産直後の一定期間内に夫婦両方が子育てのために休業したことを前提に、育児休業給付金で67%支給されていたものにさらに13%上乗せされるというもの。
出産後(産婦の場合は産後休業終了後)8週間以内に14日以上取得した場合の育休期間が支給対象となり、支給日数は28日までが上限となります。
配偶者がいない場合は片親のみ休業も可とするなど、いくつか例外もあるので確認しておきましょう」
もう一つ新しく開始されたのが「育児時短就業給付金制度」です。
「2歳までの子どもを養育する雇用保険被保険者が時短就業したときに、時短前よりも賃金が下がった場合、おおむね賃金の10%が支給されるという制度です。どちらも子育てしながら働く人にとってはとてもありがたい制度ですね」
取得が決まったら早めに相談を!
産休・育休制度を取得するときのポイント

ここからは、取得する際の報告や業務の引継ぎなどにおけるポイントを紹介します。Q&A方式で、櫻井先生にアドバイスいただきました。
Q1.企業や上司にはいつまでに報告するとよいでしょうか。
A.なるべく早めに報告しましょう。
「出産は企業にとっても喜ばしいことですが、それによる人員計画は悩みの一つとなります。規模や業種にもよりますが、代替人員の新規採用が難しい企業ほど、早めに教えてほしいというのが本音。代替人員を手配するのにどのくらいの期間が必要かを配慮し、時間がかかりそうであればなるべく早めに上司に相談するようにしましょう。
法律上は、休業を取得する1カ月前までの申し出が必要とされており、企業は申し出が遅れたぶんだけ休業開始日を遅らせることができるとされています」
Q2.業務の引継ぎのためにやるべきこととは?
A.業務内容をリストアップしましょう。
「まずは自分が現在行っている業務内容をリストアップするといいですね。場合によっては、簡単な業務マニュアルのようなものを作成しておくと、職場としては助かるはず。『何をやっておくべきか』よりも、『何を準備しておけば業務代替者が困らないか』を考えながら準備を進めましょう」
Q3.産休・育休を取得するうえでやってはいけないこととは?
A.企業や同僚に迷惑をかけないことが大切です。
「たとえば、退職予定であるにもかかわらず、偽って育休を取得することは避けましょう。育休に関しては、退職予定者は原則対象にならず、給付金の受給はできません。
ないとは思いますが、給付金目的で、育休後の復帰の意志を偽ると、その企業が代替要員を有期雇用等で探していた場合、迷惑がかかります。当たり前のことですが、企業や同僚の立場を考えながら取得しましょう」
“育休=取りにくい”の概念を変える!
産休・育休取得者のために周りができること

産休・育休を取得する同僚を送り出す側は、取得者に対して何ができるのでしょうか。こちらもQ&Aでお答えいただきました。
Q1.産休や育休で同僚がチームから抜ける場合、事前にしておくとよいことは?
A.引継ぎ業務の情報共有をしっかり行っておきましょう
「取得者側のポイントと重複しますが、まずは休業予定の同僚のタスクを一覧にし、優先度や進行状況を明確にすること。業務の期限や重要なポイントも聞いておくと、引継ぎがスムーズになります。
日常的な業務や特定のツール、システムの使い方など、休業予定の同僚が行っている作業を確認し、簡単なマニュアルを作成するのもいいでしょう。声を掛け合いながら準備をするのが大切です。
あとは、重要な知識や業務のノウハウをチーム全体に伝える時間を設定し、後任者が困らないようにサポートすることが大切です」
Q2.休業者分の業務をチームで分配する際のポイントは?
A.定期的に業務の再分配をし、負担が偏らないようにしましょう。
「一人のメンバーに負担が偏らないようにすることが大切。チーム全体で業務を共有し合い、必要に応じて再分配していくといいでしょう」

Q3.産休・育休中はどんなフォローが必要?
A.休業中の業務をサポートし合える体制を整えましょう
「たとえば産後パパ育休制度を使い、短期間の休業を取得するメンバーがいる場合、ミーティング結果を定期的に共有するなど、休業者が業務の進行状況を把握できるようにすると、復帰がスムーズにいきます。
また、休業者が業務のなかで重要な役割を担っていたり、営業などで特定のクライアントを担当していたりする場合、休業中でも連絡を取り確認しなければならない事案が発生することがあります。
そういったときに備え、休業中のサポート方法や緊急時の連絡方法を事前に決めておきましょう。あくまで休業中なので、確認に留める範囲内での方法を考えるのが大切です」
Q4.産休・育休を気兼ねなく取れる職場にするためには?
A.お互いに心配りを大切にしましょう
「産休・育休取得者は、休業前にチームに感謝の気持ちを伝えるといいでしょう。反対に、同僚からは育休取得者へ励ましの言葉を送るといいと思います。ささやかなことではありますが、言葉を掛け合いコミュニケーションを取っておくと、気持ちよく休業期間を迎えることができるはずです」
産休・育休取得者を気持ちよく送り出すためには、産休・育休取得者以外も制度を把握し、休業前に入念な事前準備を行っておくことが大切です。少子化が進む世の中だからこそ、当事者も周りもそれぞれの立場で、子育てと仕事を両立させていくためにできることを考えていきましょう。
Profile

社会保険労務士 / 櫻井純明
トーワ社会保険労務士・FP事務所代表。社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー。銀行勤務を経て中小医薬品販売会社の会社経営に参画。そのかたわら、2021年に個人事務所を開設。社会保険労務士事業として、オンラインを活用した産休・育休支援サービス事業を行っている。2児のパパ。
HP
産休NAVI・育休NAVI
取材・文=清水由香利(Playce)