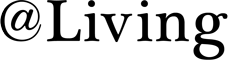毎年4月22日はアースデイ。1970年のこの日、アメリカの上院議員が環境問題の討論集会を開催したことをきっかけに定められました。55回目を迎える今年のテーマは「Our Power, Our Planet」。再生可能エネルギーを中心に電気について考える機会としています。
そこで、エネルギー問題の課題や取り組み状況、個人が日常生活でできることなどを、環境エネルギー学者の鈴木政史先生にうかがいました。
CONTENTS
危機的な状況を回避するために
必要なクリーンエネルギーとは

エネルギーは、私たちが快適な生活を送るために欠かせないもの。電気などに加工された状態で、私たち一般家庭やビルに届けられるほか、電車を走らせたり、工場を運営したりするために使われています。
私たちは現在、エネルギーに対して二つの課題を抱えている、と鈴木先生は語ります。
「一つ目は、二酸化炭素の増加や大気汚染の原因である化石燃料(石油や石炭、天然ガス)から、自然の力を活用した再生可能エネルギーに変えていくべきという課題。再生可能エネルギーは、二酸化炭素の排出量が少なく半永久的に繰り返し利用することができます。
二つ目は、地球温暖化を止めるために再生可能エネルギーをさらに導入していくべきという課題です」(環境エネルギー学者・鈴木政史先生、以下同)
2015年に国連で採択されたパリ協定では、『世界の平均気温上昇を産業革命(18世紀後半~19世紀)以前と比べて、2℃よりも十分に低く保ち、1.5℃以下に抑える努力をする』という長期目標が掲げられました。その実現のために、196の国と地域が再生可能エネルギーの導入を進めています。

再生可能エネルギーには、太陽光、水力、風力、地熱、バイオマスなどがあり、いずれも自然界の力を利用して作り出されます。
これらが近年注目を集める大きな理由は、発電時に温室効果ガスがほとんど排出されないから。またエネルギー源が枯渇せず、国内で繰り返し生産できるため、エネルギー自給率を向上させられるといわれています。そして多くの再生可能エネルギーは、環境への負荷が少ないクリーンエネルギーと捉えられます。
しかし経済産業省によると、日本における年間の発電電力量のうち再生可能エネルギーの割合は21.7%(2022年度)。化石燃料の割合のほうが高いのが現状です。日本政府は、2030年までに温室効果ガス排出量を46%削減、2050年にカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする)の実現を目標に掲げており、これを達成するためには、再生可能エネルギーのさらなる普及が必要です。
「昨今ニュースにもなっている記録的な猛暑やゲリラ豪雨、山火事などは、地球温暖化による気候変動が影響していると考えられます。今後、世界各国がクリーンエネルギーを選択しない場合、異常気象が頻発し、社会全体が危機的な状況に陥ると考えたほうがいいでしょう」
窓に貼れる太陽電池や牛のふん尿を使った発電も!?
再生可能エネルギーの最新技術

平野部が少ない日本では、地理的な条件が整わないため再生可能エネルギーを導入しにくいという問題がありました。しかし最近では、地理的条件を乗り越えるような再生可能エネルギーも生まれ始めています。
「今もっとも普及している再生可能エネルギーは太陽光発電ですが、次世代型としてフィルムのように薄く、窓ガラスに貼ることもできるペロブスカイト太陽電池が注目を集めています。既存のビルにも設置できるため、太陽光発電へのハードルが下がると思われます。
この電池の主要な材料はヨウ素ですが、日本は世界シェア30%(世界2位)を占めていることもあり、日本政府も技術の実用化を期待しています」

「水力発電には、大きなダムを必要とせずに発電できる小水力発電があります。発電容量は1万kW以下ですが、多くの水量を必要とせず、既存の河川や農業用水などが使えるため、環境配慮型の発電設備といえます。
そして風力発電には、浮体式の洋上風力発電が生まれています。これは、浮力のある構造物に風車を設置し、海に浮かべる新しい発電設備。日本の海は海岸線から水深が深くなるため、海底に土台を設置するのは難しいと言われていましたが、この技術が生まれてから普及拡大に注目が集まっています。
海洋エネルギーを使った発電には、波の運動エネルギーを利用する波力発電や、潮の満ち引きを利用する潮力発電もあります」

日本ならではの地理的条件や土地活用から生まれる再生可能エネルギーもあり、さらなる普及拡大が期待されています。
「日本は世界第3位の地熱資源量(2,347万kW)を持っているため、豊かな資源を生かした地熱発電のポテンシャルが高いと言われます。また国土の約7割が森林であるため、間伐材を利用したバイオマス発電も普及拡大が待たれます。
ユニークな再生可能エネルギーには、北海道でのバイオガス発電が挙げられます。酪農において牛などの家畜から出るふん尿を発酵させてメタンガスを生成し、これをエネルギーとする発電です」
「再生可能エネルギーは以前よりも発電価格が下がってきていることもあり、ビジネスとして十分取り入れられるレベルになっています」、と鈴木先生。今後は、再生可能エネルギーをさらに取り入れようとする社会的な機運の高まりで、急速に普及する可能性はありそうです。
売電収入を得られる事例も!
企業や自治体の取り組み

ここからは、鈴木先生に一般企業や自治体の取り組み事例についてご説明いただきます。再生可能エネルギーの課題にも触れていただきました。
エネルギーの消費量が多い大手企業は、どう取り組む?

「東急電鉄は、2022年4月から再生可能エネルギー由来の電力100%で、全路線での運行や駅の運営を行っています。日本では鉄道事業に対し、とくに規制があるわけではありませんが、自主的に再生可能エネルギーを発電源とした電力を積極的に購入しています。
商船三井は、風の力で船舶の推進力を補助する風力補助推進システムを開発しました。強くて軽く、回転もできる帆を独自に開発して船舶に搭載。すでに大きな商船にも搭載されており、運航を開始しています」
鉄道業界や海運業界のように大きなエネルギーを消費している企業は、一般消費者から理解を得る必要があり、海外ではすでにそういった気運が高まっていると鈴木先生は話します。
「マイクロソフトやグーグルなどのデータセンターでは、システムの冷却に伴う電力の消費量が非常に大きいと言われています。そのようなところでは化石燃料ベースではなく、再生可能エネルギーベースの電力を使用する方向に変わっています」
売電収入1億円以上の自治体も! 地域の取り組み事例

日本の地方自治体でも、二酸化炭素排出量に考慮した独自の取り組みや、地域ならではの特性を活かして二酸化炭素排出量削減に取り組む例が見られます。2021年に地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の一部が改正され、地方自治体の施策目標が追加されたことも影響しているかもしれません。
「脱炭素社会への実現に向けた神奈川県川崎市の取り組みは、自治体のなかでも優れた取り組みと言えます。産業系の二酸化炭素排出量が約76%を占める同市は、廃棄物発電を市内で循環させ、再生可能エネルギーを普及拡大させるために地域エネルギー会社『川崎未来エナジー株式会社』を設立。2023年から事業を開始しています。
横浜市は太平洋に面した立地を活かして、ブルーカーボンによる二酸化炭素排出削減に取り組んでいます。ブルーカーボンとは、海草や海藻などの海洋植物が二酸化炭素を取り込んで作り出す炭素のこと。横浜市は地元企業とタッグを組んで、このブルーカーボンの活用や普及に努めています」

地域によっては、再生可能エネルギーを作り出して売電収入を生み出し、収益の一部を住民に還元する例も見られます。たとえば、福島県にある土湯(つちゆ)温泉では、豊富な湯量を利用した地熱発電所を設立。年間に約300万kWの電力を供給し、売電して1億2000万円の収入を得ています。
「再生可能エネルギーを所有した場合、そこで発電した電力は住民のものになるため、電力会社から購入するよりも低価格で電力を利用できる事例も。地域に自家発電設備が用意されていると、台風などの災害時でも電力へアクセスしやすくなるというメリットもあります。
近年は、そのような施設を見学したり、体験できたりする発電ツアーもあるので、興味があればぜひ訪れてみてください」
所得に関わらず電気代などのエネルギー価格が一律であることは、エネルギー価格の高騰により、生活に必要なエネルギーサービスを受けられなくなる「エネルギー貧困」を招きます。しかし多くの地域で売電収入を得られるようになれば、これらの問題も改善するかもしれません。
正義ばかりじゃない。
再生可能エネルギーの隠された課題

二酸化炭素をほとんど排出しないといわれる再生可能エネルギーですが、実は課題もあると鈴木先生はいいます。
「たとえば、日本で最も普及している太陽光発電には、景観破壊やリサイクルの問題が挙げられます。今後5年間で製品寿命が切れる太陽光パネルが増加するため、どのようにリサイクルするべきかという課題は、業界としての大きな課題です。
バイオマス発電においては、日本産の間伐材を100%使用せず、海外からの輸入木質燃料やパーム油などの液体燃料を発電に利用することが問題になっています。輸送時に莫大なエネルギーを消費するため、逆に二酸化炭素排出量が増加してしまうのです」
SDGsの目標7は『エネルギーをみんなに、そしてクリーンに』。エネルギーをクリーンにするためには再生可能エネルギーの普及が欠かせませんが、他の目標と抵触しないような進め方を選ぶ必要があるのです。
エネルギー問題解決に向けて
個人としてできること
地球全体の二酸化炭素排出量削減のために、私たち個人もエネルギー消費に対してより敏感でありたいもの。鈴木先生に教えていただいた、個人で意識し行動できることをご紹介します。
1.地産地消に取り組む

「地産地消とは、ある地域で生産された農林水産物をその地域内で消費すること。たとえばスーパーマーケットで買い物をするときに、できるだけ近隣で作られたものを購入するといいでしょう。というのも、輸送時に発生する二酸化炭素排出量は莫大なものになるからです」
「このような行動であれば、個人で太陽光パネルを導入するよりも気軽に行えます」と鈴木先生。また最近の消費者は、商品を選ぶ際に認証制度を意識する傾向にあるとのこと。
今後、“クリーンエネルギーで作られた”という認証マークができた際は、認証マークが付いた商品を選ぶのもいいかもしれません。
2.モノ消費より、コト消費を選ぶ

「モノ消費とは、お金を使う際に『商品を所有すること』を重視した消費行動です。一方、コト消費とは、旅行やアクティビティなど『体験すること』に重きを置いた消費形態。モノ消費を重視すると、製品の生産、消費、処分時に莫大なエネルギーを使います。
たとえば、モノ消費の価値観で自動車を所有するのではなく、コト消費の価値観でライドシェア(一般ドライバーによる相乗りサービス)を利用するとエネルギー消費を減少できます」
3.ESG投資を始める

「ESG投資とは、環境、社会、ガバナンスという3つの要素を考慮して行う投資のこと。投資をする際に、クリーンエネルギーを取り入れている企業を選ぶと、環境問題解決への貢献につながります」
エネルギー消費を意識して行動することは、地球を大切にすることにもつながります。気候変動による異常気象が増えている今、あらためてエネルギー問題について考えてみませんか。
Profile

環境エネルギー学者 / 鈴木政史
上智大学大学院 地球環境学研究科 地球環境学専攻 教授。国連気候変動枠組み条約事務局(UNFCCC)および国連経済社会局(UN DESA)持続可能な開発委員会ファイナンス部コンサルタント。主たる研究領域は、企業の環境・エネルギー経営戦略やクリーンエネルギー技術のイノベーション・普及。政策に近い研究課題にも数多く取り組む。
上智大学大学院
取材・文=星野祐子(Playce)