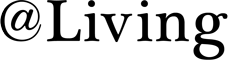日常のさまざまなシーンでインターネットとつながり、音楽・映画といったエンタメから買い物、さらに教育の分野でも、オンライン化が加速しています。ITに詳しくない人も日々の暮らしを通じて、物理的な接点のある社会「オフライン」の中に、付加価値としてデジタル社会、つまり「オンライン」が浸透していることを実感しているでしょう。
世界では、中国やアメリカを中心に、個人が常時スマホを携帯して、街のいたるところにカメラやセンサーが設置され、私たちの行動はすべてオンラインデータ化されて、“データを集める”という点においてビジネスの世界では、オフラインの必要性がなくなろうとしています。一方、日本の“オフラインを軸にオンラインを活かす”方法は、「ビフォアデジタル」といわれる古い概念。オンとオフの主従が逆転した、“オフラインがデジタルの世界に内包された世界”=「アフターデジタル」がいま、世界のビジネスの主役に躍り出ているのです。
この新たなるデジタルの世界を、事例とともに1冊にまとめたのが、『アフターデジタル-オフラインのない時代に生き残る-』です。@Livingでおなじみのブックセラピスト、元木忍さんが、著者のひとりである藤井保文さんを訪ね、この本が生まれたきっかけや、アフターデジタルの現在と今後の見通しなどを伺いました。

『アフターデジタル -オフラインのない時代に生き残る-』
藤井保文・尾原和啓 / 日経BP
ITを使って生活をより良い方向へ変革させる「デジタルトランスフォーメーション」。この言葉は知っていても、実際に「何をしたらよいのか分からない」と嘆くビジネスパーソンに向け、すべてがオンライン化された世界「アフターデジタル」の本質を解説しながら、その方法論を教えてくれるのが本書。驚くべき進化を遂げた世界のビジネス事例も、たっぷり紹介されています。
日本は妄想力を具現化した世界観で勝負せよ!
元木忍さん(以下、元木):コロナ禍の在宅勤務で、Zoomなどを活用したオンライン会議が浸透しましたが、私の周囲ではデジタルを使うことにストレスを感じている知人も多くいて、こうしたデジタルに不安を訴える人に最適な本がないかと、あれこれ読みあさっていた時に手に取ったのが、この本でした。ビジネス書ですが、ビジネスパーソン以外にも広く、そしてとても多くの方に読まれているそうですね。
藤井保文さん(以下、藤井):昨年の3月に刊行され、現在までに8万5000部を発行しています。自分でもここまで読んでいただけるとは思ってもみなかったですね。
元木:おもに中国の新しいビジネスが紹介されていますね。注文から30分以内に配送してくれるアリババのOMO(オンラインとオフラインの融合)型スーパー「フーマー」や無人コンビニ「Jian24」など、先進的な事例に驚きつつ、一方で、デジタルに対して日本が遅れをとっている現状に、ある種の“恐怖”も感じました。
藤井: 読まれた方のレビューも拝見しましたが、「ためになった」という意見のほか、「怖い」とか「こうなってはいけない」というご意見も多くいただきましたね。

元木:本題に入る前に、藤井さんのプロフィールを伺ってもいいでしょうか? 26歳で就職と、少し遅れて社会に出たのは、まだ好きなことをやっていたいとか、今は就職するタイミングじゃないといった迷いがあったからですか?
藤井:それはありましたね。大学卒業後にいったん、フリーターとして音楽や映像制作をしていました。仕事にしたいというより、音楽や映像で自己表現を続けたいと考えていたんです。翌年に大学院へ進み、そろそろ社会に出ないとな、と感じ、修了と同時に、UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインコンサルティングなどの事業を展開するビービットに就職しました。入社後はずっとUXの仕事に就きまして、2014年に台湾、2017年に中国へ赴任して中華圏の仕事に携わりました。
元木:ご苦労されたことはありましたか?
藤井:26歳まで仕事をしていないので、当初は接客時の言葉遣いのマナーから教わり、ビジネスの世界に慣れるまでに1〜2年はかかりましたね。台湾に赴任した際も、英語の読み書きはできても、会話ができないのでコミュニケーションに苦慮しました。「どうやったら周囲から信頼され、効率よく一緒に仕事ができるか」を問い続けながらやってきて、何とか乗り越えた時、任される仕事が急に増えていきました。私は社内にある仕事を頼まれるより、やりたいプロジェクトを自分で営業して取ってくるというスタイルで仕事を広げていきましたが、中華圏での仕事で評価され、ビジネスマンとしてだいぶ成長したと思います。
元木:それが土壌にあって『アフターデジタル』を書くきっかけとなったのですか?
藤井:ビービットでは、さまざまな日本企業の幹部の方に、中国の新しいビジネスの仕組みなどを説明する、「チャイナトリップ」と称した「中国デジタル環境視察合宿」を行っていました。2018年に『アフターデジタル』の共著者となる、IT評論家の尾原和啓さんをこのチャイナトリップに招待をしたら、視察を終えた後に「藤井さん、これはめちゃくちゃ面白いから本にしませんか」と声掛けいただいたのがきっかけですね。
元木:共著者の尾原さんもびっくりされたんでしょうね。中国ではIDカードでタクシーに乗り、キャッシュレスで支払うのが当たり前ですから。私も含め、昔を知りすぎている人にとって現在の中国は別世界ですよね。この現状を伝える本を出版したいという気持ちはわかります。
藤井:ただ忙しかったので、最初はほかの方にインタビューをまとめてもらって、私が推敲する形で進めていきました。しかし、話をまとめていただくだけでは伝わりにくいことが多々あり、中国に住んでいるから書ける肌感みたいなものもあって、結局自分で執筆することに。結果として、本書の9割は私が書くことになりました(笑)。
元木:この本を読むと、日本人経営者のあるあるとか、中国人経営者らしさとか散りばめられていますよね。この驚くべき状況を、日本のビジネスパーソンに伝えたいという思いもあったのですか?
藤井:はい、それも理由のひとつです。当時の日本では、デジタル化は不可欠とか、デジタルで生活を豊かにする「デジタルトランスフォーメーション」が必要だとか言われる本当の意味や、海外で実際に起きているアクションの本質がまったく理解されていない、とは感じていました。バズワードとしては認識していても 視点や視野の意味合いではまだ見えていない状況でした。日本の有名な経営者の方が「チャイナトリップ」にいらっしゃっても、みなさん一様に驚かれていましたから、本書を出版することで、ビジネスパーソンだけではなく、日本企業にもバリューがあるかもしれないという思いもありました。
元木:私自身も、日本はまだ最先端だと思い込んでいましたが、中国に追い抜かれたことを、まだ認めたくない人も多いかもしれませんね。
ちょっと答えにくい質問かもしれませんが、先進度合いではアメリカと中国のどっちが上だとお考えですか?
藤井:2国を比べるのは難しいですね。例えばGAFA(編集部注:ガーファ。Google、Apple、Facebook、Amazonという、米国発のITプラットフォーマーの総称。)は全部アメリカベースの企業ですし、時価総額ランキングの上位10社のうち7社はアメリカ企業が占めています(※)から、この点にスポットをあてれば、アメリカの方が進んでいるといえます。しかし、14億人という人口があって、個人のあらゆる情報が社会に行き交っている状況は、世界でも中国でしか生まれていません。ものづくりやブランドづくりは、アメリカの方がうまいとは思いますが、AIやデータ、デジタルテクノロジーを活用し、オンラインとオフラインの双方を使う、という意味合いでは、中国の方が先行しています。総合力で考えるとどっちもどっちだと思いますね。
※World Stock Market Capitalization Ranking 2020(2020年7月末時点)
元木:ユーザーから集めたビッグデータといわれる情報を、きちんと活用できている実例ですね。たしかにビッグデータに関しては、中国の方がうまく使っている印象が強いです。
藤井:以前、アリババの国際UXの責任者に聞いた話ですが、彼は欧米系半分、アジア系半分で自分のチームを作ると教えてくれました。新しいアイデアを生み出すのはアメリカ人が得意で、アジア人はそれを組み合わせたり、深めていくことが得意なので、欧米人が企画をたて、アジアの人材がそれを突き詰めていく構造がチームとして最適だとおっしゃっていました。
元木:世界のビジネスでは、日本はどんなポジションにいるんでしょうか?
藤井:いろいろな角度から言えますが、得意分野でいうと“プロセス主義”的なところがかなりあるので、トヨタ自動車の“かんばん方式”のような、プロセスを磨き上げさせたら一番凄いと思います。ただ、どうしても手段が目的化しやすいところがあって、例えば、実際にせっせとユーザーデータを集めている企業の方が、何のために集めているかを答えられないというケースも多いのです。
元木:私も経験がありますが、集めたデータをどう活用するかを社内で議論しても答えが出ないんですよ。データで何をするかより、データを持っていることに胸を張っている企業が多いことを実感しました。まさに手段が目的化している実例ですね(笑)。

藤井:ここは一番に変えていかなくてはいけないのですが、日本人の性質なので簡単には変わらないでしょうね。言い続けるしかない(笑)。
元木:日本人特有の概念みたいなものですかね。変えられない企業体質とか……。
藤井:『シン・ニホン -AI×データ時代における日本の再生と人材育成-』(ニューズピックス)の著者である安宅和人さんは、何でも創れる時代になり、自分が思い描いた妄想を具現化することがどんどん容易になっていくので、今後本当に必要なものは“妄想力”である、とおっしゃっています。独特の世界観を作らせたら日本人は強いですから、妄想を妄想に留めず具現化までいければ、世界のトップに立てると思っています。アニメでも漫画でもゲームでも、さまざまな物語を細部まで作り込みつくっているのは日本人だと思うので、素養は十分ありますね。
以前、星野リゾート代表の星野佳路さんが、日本人がよく使うおもてなしについて「おもてなしとは相手のことを慮って先回りすることではない」とおっしゃっています。私も同感で、先回りすることは、西洋でいう相手に仕えるサーブの概念であり、日本のいうおもてなしは、小物の配置、所作やルールが徹底された世界観を提供することで相手に「なんて完成されて行き届いた世界なんだ」と感じてもらうことだと考えています。
これも、まさに“妄想力の具現化”なんですね。また、小山薫堂さんがプロデュースをした「くまもとサプライズ」も、県外の人を誘致するのではなく、くまもんを使い、熊本県民が熊本のいいところを発見することをメインの目的に置いていたので、県民の参加度がまったく違いますし、結果的にくまもんも有名なキャラクターに育ちました。これも妄想力を使って世界観をつくるという図式に近く、日本の得意な部分を活かすことで成功に導いた好例だといえます。これをデジタルで実現できたら今後はグローバルで強みになると思います。
『アフターデジタル』に続き、藤井さんは続編となる『アフターデジタル2 UXと自由』を2020年7月に上梓。世界がコロナ禍にあえぐ今、アフターデジタルの世界にどのような変化が起きているのでしょうか?