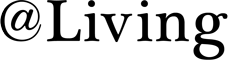「夏も近づく八十八夜〜♪」と、茶摘み歌で知られる「八十八夜」。今年は5月1日にあたります。新緑がまぶしいこの時季に摘まれた新茶は、香り高く味わいも格別。一年の無病息災を願う縁起物として、古くから親しまれてきました。
そんな特別な新茶だからこそ、丁寧に淹れてその魅力を存分に味わいたいもの。今回は、日本三大銘茶のひとつ、「狭山茶(さやまちゃ)」を製茶し、江戸時代から続く茶園「奥富園(おくとみえん)」の15代目・奥富雅浩さんに、八十八夜の由来や新茶をよりおいしく味わうコツ、日本茶の豆知識などを教えていただきました。
CONTENTS
お茶にとって特別な
「八十八夜」とは?

「八十八夜」とは、立春から数えて88日目にあたる日。毎年5月初旬ごろにやってきます。三寒四温が終わり寒暖差が落ち着くこの時季は、霜がおりる心配もないため、農作業に本腰を入れるのに最適なタイミング。日本では古くから、暮らしの節目として大切にされてきました。
「お茶にとっても八十八夜は、特別な意味を持ちます。というのも、寒い冬のあいだにじっくりと養分を蓄えた新芽が、この時季に摘みごろになるから。香り高くやわらかな『新茶』の茶摘みを始めるタイミングなのです。
その年の生育状況や気候にもよりますが、茶摘みは萌芽から約4週間が経ったころから始めます。当園の場合、今年(2025年)は4月21日に茶摘みがスタートしました」(奥富園15代目・奥富雅浩さん、以下同)
科学的にも実証済み!
新茶ならではのおいしさ
八十八夜のころに摘まれた茶葉で作る「新茶」は、その年に初めて収穫された、いわばお茶の「初物」。日本では昔から、季節の初めに口にするものには生命力が宿るとされていて、初物を食べることで福を招き、長寿を願うという文化があります。
新茶もまた、単に新しく収穫されたお茶というだけでなく、一年の始まりに感謝し、健やかな日々を願って味わう、特別な一杯なのです。
「昔から、新茶を飲むと無病息災で過ごせるといわれてきたように、健康と長寿を願う縁起物として親しまれてきました。当園も、毎年新茶を心待ちにしてくださっているお客様が多く、ご自宅用やご贈答用にお買い求めいただいています」

新茶が多くの人に好まれるのは、初物としてのありがたみだけでなく、味わいそのものにも魅力があるから。実はそのおいしさには、科学的な裏づけがあるのです。
「茶樹は、冬の寒さにじっと耐え養分をたっぷりと蓄えます。その養分を使って伸びるので、一番茶の新芽には、うま味成分であるテアニンが豊富に含まれているのです。さらに、夏よりも日差しがやわらかく気温も穏かなこの時季は、渋みのもととなるカテキンの生成も控えめ。
つまり、新茶は春の穏やかな日差しのなかで育つからこそ、渋みが少なくまろやかで、しっかりとしたうまみを感じられるお茶になるのです。新茶は、日本茶ならではの“うまみ”を最も堪能できるお茶といえます」
新茶をよりおいしくいただくコツ3つ
淹れ方にもこだわると、うまみと香りが豊かな新茶のおいしさをより味わうことができます。奥富さんに、おいしく淹れるコツを教えていただきました。
コツ1.陶器の急須を使う

「新茶にかぎらず、お茶は陶器の急須で淹れるのがおすすめです。なぜなら陶器の急須は、茶葉が持つ渋み成分を適度に吸着してくれるから。それにより、お茶がまろやかになるんです。ガラス製のティーポットは、新茶の鮮やかな緑色がとても素敵に見え、目でも楽しむことができますが、まろやかにする効果は期待できません。
また急須を返して茶碗に注ぐ動きもとても大事。返すたびに急須の中で茶葉が開き、お茶の成分がしっかり抽出され、香りや味がさらによくなります」
コツ2.湯温は70〜80℃。蒸らし時間は茶種に合わせて変える

「お茶には三大成分と呼ばれるものがあります。先ほども話したうまみ成分の『テアニン』、お茶の特徴的な渋みのもととなる『カテキン』、苦みをもつ『カフェイン』です。テアニンは湯温にかかわらず時間をかけることで抽出でき、カテキンやカフェインは温度が高いほど抽出しやすくなります。
そのため、お茶を淹れる温度を70~80℃にすると、渋み・苦みが抑えられ、うまみを引き出すことができます。
蒸らし時間はお茶の茶種(製法)によって少し異なり、深蒸し茶であれば40秒ほど、普通煎茶(浅蒸し茶)であれば1分ほどを目安にするとよいでしょう。新茶の場合は、より香りを楽しみたいなら少し温度を高めにし、そのぶん蒸らし時間を少し短めにしてみてください」
コツ3.アイスで味わうなら冷やしながら3時間以上抽出

「もちろん水出しで新茶を楽しむこともできます。その場合は、水1ℓあたり10~15gの茶葉を入れ、冷蔵庫で3時間以上冷やしながら抽出します。じっくりと時間をかけて抽出するのでうまみが強く、さらに甘みも感じる仕上がりになります。
温度が低いので、カテキンやカフェインが抑えられたとても飲みやすい味わいです。ただし、香りの成分は揮発性なので、水出しでは感じにくくなります」
一緒にいただくと相乗効果!
新茶の魅力を引き出すおすすめお菓子

新茶の豊かな味わいを引き立ててくれるもの、といえばお茶請けでしょう。どんなお菓子と合わせるのがよいのでしょうか。
「深蒸しタイプの新茶は、しっかりと濃く、お菓子の風味に負けない強さがあるので、和菓子ならこっくり甘いどらやきが合いますね。またクリームを使った洋菓子との組み合わせもおすすめです。
淡い色合いでさっぱりとした浅蒸しタイプの新茶には、落雁(らくがん)や和三盆(わさんぼん)など、繊細な甘みのお干菓子はいかがでしょうか。あんこを使ったものでも、甘さ控えめタイプであれば相性はよいと思います」
よく耳にする「やぶきた」とは?
その魅力とその他のおすすめ品種

お茶に詳しくない人も、一度は「やぶきた」という単語を聞いたことがあるでしょう。これは日本茶において最もよく知られ、広く栽培されている品種の名前。全国の茶園の7割以上がこの品種を育てている、まさに“日本茶のスタンダード”といえる存在です。
「『やぶきた』が誕生したのは、1908年、明治時代にまでさかのぼります。場所は静岡県。茶業試験場の杉山彦三郎氏が、優れた風味と耐寒性をもつ茶樹として、自宅の竹やぶの北側にあった茶の木を選抜したことが名前の由来です。
やぶきたは、その安定した品質と収量により全国の茶樹園にたちまち広まりました。バランスのよい味わいと香りのおかげで消費者からの支持も高まり、一気に日本茶を代表する品種になったのです」
「やぶきた」は、気品のある爽やかな香りとうまみ、甘み、渋みのバランスのよさが魅力で、日常使いはもちろん贈りものにも活躍する万能型の品種。奥富園でも「やぶきた」は主力の茶葉として取り扱っているそうです。
加えて最近では、「やぶきた」以外にもさまざまな品種が誕生しています。なかでも狭山オリジナルの品種は存在感を増していて、香りに特徴を持つ茶葉が多くあるそう。その一部をご紹介します。
花のような華やかな香りに心がほぐれる「ふくみどり」

「1986年に育成された『ふくみどり』は、『やぶきた』と古くからある狭山の品種『さやまみどり』を掛け合わせた品種。香りがとても強く、狭山でも高級茶として扱われています。口に含むと花のような香りがふわりと広がり、心が軽やかにほどけていく、そんな豊かな味わいのお茶です。
当園では、昨年の『ふくみどり』はすでに完売していており、今年のものは5月半ば以降に販売開始となる見込みです」
ミルキーで甘いメルヘンな香りの「ゆめわかば」

「僕のお気に入りは『ゆめわかば』。まずはストーリーの面白さに惹かれました。実はこのお茶、味や香りが特徴的すぎることから開発段階で一度捨てられそうになったんです。それを、他県から視察に訪れた茶業機関の方が『このまま埋もれさせるなんてもったいない。絶対に品種化すべき!』と強く推したことで品種化に至ったんです。
もちろんやさしい甘さと香りという、お茶としての特徴にも注目しています。現在では、そのユニークな風味が再評価され、注目を集める品種となりました。当園でも取り扱っていて、お茶の製造を始めると、工場全体がふんわり甘い、まるでメルヘンの世界みたいな香りに包まれるんです。まさに名前のとおり、夢の中で出会う若葉を思わせるミルキーで甘い香りを楽しめます」
より深く楽しむために知っておきたい!
茶園が教える日本茶豆知識
品種ごとの個性や背景を知ることで、日本茶の世界はますます豊かに、そして奥深く感じられるようになります。最後に、よりおいしくお茶を楽しむための豆知識も教えていただきました。
豆知識1.茶葉をあえて“しおれさせる”製法がある
「伝統的な製法を守りながらも、生産者たちは茶葉の持ち味を引き出そうと日々工夫を重ねているため、実は日本茶の製法は少しずつ進化を続けています。
たとえば当園では、先ほどご紹介した『ゆめわかば』を『萎凋(いちょう)』と呼ばれる工程をはさみ製造しています」

「萎凋とは、摘んだ茶葉を天日に当てたり風を送ったりしてしおれさせ、葉の中にある酵素を働かせる工程。これにより、花や果物のようなやわらかい香りが引き出されるんです。『ゆめわかば』のやさしくまろやかな味わいは、このひと手間によってさらに際立ちます」
豆知識2.「抹茶=煎茶を粉にしたもの」ではない

「よく見かける煎茶、玉露、抹茶は、それぞれ製法が異なります。煎茶は、日光をたっぷり浴びて育った茶葉を蒸して揉みながら乾燥させた、もっとも一般的なお茶。爽やかな渋みと、ほどよいうまみが特徴です。
玉露と抹茶は、収穫前の茶畑に覆いをかけて日光を遮ることで、テアニンなどのうまみ成分を増やし、葉の色も鮮やかで濃い緑にします。そうやって育てた茶の葉を、煎茶と同じように蒸して揉みながら乾かしたものが玉露、蒸したあとにまったく揉まずに乾かしたものが抹茶の原料となる『碾茶(てんちゃ)』になります。
『煎茶を粉にしたものが抹茶ですか?』と聞かれることがありますが、煎茶と抹茶は栽培方法も製造方法もまったく異なるのです。抹茶は揉まずに乾かすことで茎や葉脈まで取り除き、それを石臼で細かく挽いて粉末状にしています」
豆知識3.開封したお茶はどのくらいで飲み切るのがいい?

「お茶は鮮度が命。開封後はふた付きの茶筒などで密閉し、常温で1ヶ月以内を目安に飲みきるのが理想です。これからの季節は水出しで、冷たい日本茶を楽しむのもおすすめ。水出しは茶葉を多めに使うので、鮮度の高いうちに飲みきりたい新茶にもぴったりです」
一年で最も日本茶が香り立ち、味わい深くなる特別な季節が到来。旬の一杯には、心をほどくような豊かさがあります。この時季ならではの贅沢をぜひ体験してみませんか? お気に入りの一杯が、きっと見つかるはずです。
Profile

茶農家「奥富園」15代目 / 奥富雅浩
1980年生まれ。江戸時代から続く埼玉県狭山市の茶農家「奥富園」15代目。認定日本茶シニア・インストラクター。茶畑の管理から製造・仕上げ、小売までを一貫して手がける。煎茶、深蒸し茶、萎凋茶、焙じ茶、粉末緑茶、和紅茶、抹茶など、伝統を大切にしながら、時代に合わせて楽しめる多彩なお茶を提案している。
HP
Instagram
Facebook
狭山茶製造元 奥富園
住所:埼玉県狭山市加佐志36
Tel:04-2959-4789
営業時間:9:00~18:00
定休日:水曜
取材・文=糸井朱里 構成=Neem Tree 写真=奥富園