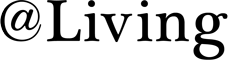この肩書を名乗る者は、日本にただひとり。【製硯師 —せいけんし-】とはいったい……?
浅草で1939年の創業以来、都内では希少な硯の工房を併設している書道用具専門店「宝研堂(ほうけんどう)」。今回編集部がたずねたのは、ここで4代目として硯を作り続けている青栁貴史さんです。
硯といっても、現代の日本に暮らす私たちにとっては普段、ほとんどなじみのない道具。小学校で書道を習ったときに使ったのが目にした最後、という人も多いでしょう。ところが、ここで20年以上に渡って硯を作り続けている青栁さんの仕事は、近年多くのメディアに注目され、特に昨年はドキュメンタリー番組『情熱大陸』(TBS)にも出演して大きな話題を集めました。
なぜなら、彼の仕事ぶりは想像を絶するほどユニークなのです。あるときは、優れた硯石を求め世界中を駆け巡るハンターに。あるときは、指先の感覚ひとつでコンマミリレベルの造形を仕上げていく職人に。そしてまたあるときは、お風呂場にまで石を持ち込んで、石紋の美しさをうっとり眺めている重度の石ホリックに!
彼がそれだけ、硯の世界に魅了される理由とはなんなのでしょうか? その根底には、筆記具としての硯の本当の姿、かつて日本にも当たり前にあった毛筆文化の豊かさを伝えたいという、純粋な思いがありました。
[ 目次 ]
・硯と毛筆の“本質”とは?
・「製硯師」の肩書きに込められた思いとは?
・硯と毛筆の新しい挑戦
・製硯の過程
・青栁貴史 渾身の3作

製硯師 / 青栁貴史
あおやぎ たかし/1979年、東京都浅草生まれ。16歳より祖父と父に作硯を師事。浅草の書道用具専門店「宝研堂」内の硯工房にて、4代目製硯師を務める。大東文化大学文学部書道学科で、非常勤講師としても活躍。若い世代に、毛筆文化の豊かさとその本質を伝える活動にも情熱を注ぐ。
毛筆は、誰もが日常的に使っていいもの
「みなさんは、硯というと“書道用具”のイメージがあるかもしれません。でも硯って、本来はただの筆記具。1500年前の中国でおおむねこの造形が決まって、それからほぼモデルチェンジもマイナーチェンジもされることなく、現代まで続いている、世界最古の筆記用具のひとつなんです」
硯が生まれた中国でこれが現在の形になったのは、約1500年前の唐代。その当時、書の教育を受けられたのは、皇帝をはじめ政(まつりごと)に携わる高官など限られた人間のみでした。青栁さんいわく、当時の硯は剣や宝石にも勝る権威の象徴であり、親から子へ代々受け継がれていくものでもあったのだそう。
「その毛筆は書道とともに海を渡って日本に伝わり、日常の筆記具として人々の暮らしに根付きました。だからほんの数十年前までは、日本人ならみんな何かを書こうと思ったら硯と墨、筆を使っていました。戦後、毛筆は日常の筆記具の中から少しずつなくなっていきますが、書道は芸術として残り、発展を続けていきます。すると日常生活から乖離した毛筆は、一般の書き手にとって“うまく書かなきゃいけない”ものになってしまった。毛筆を取り巻く現在の状況というのは、ちょうど着物文化と似たようなものかもしれませんね。着物がかつてすべての日本人の普段着であったように、毛筆だって実は誰でも日常的に使っていい。それは僕がお伝えしたい硯のありかたの本質ともいえます」

硯と毛筆の本質を伝える製硯師
硯とは、わかりやすくいえば墨汁を調理するためのおろしがねのようなもの。それは天然の石から、人の手で削り出すことで生まれます。表面には鋒鋩(ほうぼう)という目に見えない無数の凹凸があり、ここに水を加え、墨をこすることで墨汁ができるのです。材料となる石の採石地は、日本でも宮城県、山梨県、山口県などいくつかの場所があります。現代の硯は、そういった採石地の地場産業として作られている場合が多いそう。
「地域にもよりますが、日本の製硯現場では伝統的分業制が、今でも継承されています。それらの現場には石を切る人、彫る人、磨く人といった何人かの職人さんがいます。その中で例えば、技術的に秀でている人が、やがて硯作家として活躍されるケースも。石の性質ももちろん各地で違うので、採石地ごとに、その石に合った技術や造形、文化などが受け継がれているんです」
しかし、青栁さんが活動するのは採石地とはほど遠い東京の浅草。そこで名乗る製硯師という日本唯一の職業には、いったいどんな意味や思いが込められているのでしょう。