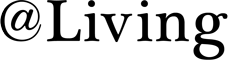既製品に小さなひと工夫=カスタマイズを加えて、 より愛着の湧く自分らしい暮らしをつくっていく。気軽なD.I.Y.や手作りを楽しむ人が増えている昨今、ファッションの世界にも「カスタマイズ」に焦点を当てたモノ作りから、時代の空気を切り取ろうとするデザイナーがいます。
1997年にシューズブランドとしてスタートし、東京・パリ・ロンドンなどでコレクションを披露してきた「maison MIHARA YASUHIRO」のデザイナー、三原康裕さん。2015年にスタートした新ライン「MIHARA YASUHIRO Modified」(ミハラヤスヒロ モディファイド)では、三原さんがこれまで個人的に収集してきたミリタリーアイテムやヴィンテージ古着を、アトリエチームの皆が手作業で解体し、1点ものの新たな洋服として再構築するという試みがなされています。
約20年間に渡り「ゼロからイチへ」の服作りに挑んできた三原さんが、いまなぜあえてのリメイク、カスタマイズに着目したのか。そこには、職人の見様見真似と独学で靴作りを始め、モノや手しごとを心底愛してきた三原さんらしい、クリエイターとしてのピュアな欲求がありました。

洋服やその歴史が持つ意味というのが
たまに「重いな」って思うときがあるんです
——無類のミリタリー好きとしても知られ、デザインにもその影響が強く感じられる三原さんですが、’15年に「モディファイド」をスタートしたそもそもの理由は何だったのでしょうか?
三原康裕さん(以下、三原):きっかけは、実はすごくくだらなくてね。僕の自宅やアトリエには、今までに収集してきた大量のミリタリー古着があるんです。もちろんいろいろな国のいろいろな年代の古着があるんだけど、全部がまったく違うモノというわけでもなくて、同じようなアイテムが5~6着ずつあるというような状況。……といっても、僕の中では似ていても全部違うモノなんだけどね。作ってる工場や年代が違うとか、縫い目が違うとか(笑)。例えば代表的なジャケットである「M-65」なんかは、70着ぐらい持っていました。
——70着の「M-65」! ちょっとした古着店のようですね。
三原:それがあまりにも多くなりすぎたから(笑)、ちょっと処分しなきゃなと、常々思っていて。そんなときに、大阪の直営店が周年を迎えるから、何か特別なモノを作りたいって相談されたんです。そこで古着を使って作ってみたアイテムが、「モディファイド」ラインを始めるきっかけになりました。


——持っていた古着をリメイクするという作業に、何かしらの手応えを感じたということでしょうか?
三原:リメイクには、イチから作ってしまうとできない面白さがあると思うんです。ファッションデザイナーに限らず、モノをゼロから作るって、意外と長い時間と手間ひまがかかる。そのわりに自分でひとつひとつじっくり手を加えていくことは、物理的に不可能なんですよね。なぜなら量産していかなきゃならないから。でも古着のリメイクなら“その場限り”。糸や生地から作るというモノ作りの長い工程を全部はじき飛ばして、思いつきでペイントしたり、パッチワークしたりしながら、なおかつ思い入れのある一点ものができちゃうんです。特に僕が好きなミリタリーやワークウエアには、大量生産されてきた洋服が持っている特有のルールというか、決まりきった感じがあるんですよ。これだけ古着を集めておいてこんなことを言うのも何なんだけど、その意味やルールみたいなものが、逆に「重いな」って感じることも実はよくあるんです。
——ミリタリー好きに多い、マニアックな視点のことですかね。ボタンやベルトの位置、そのほか細かいディテールへのこだわりだとか。
三原:そうそう。洋服って自由なようでいて、実は案外いろいろな決まりごとがあってね。まず一番の要素が、ミリタリーとかスポーツといった“フォーム”。それからシルエット、素材、スタイリングといった要素があって、僕らはそういう要素を自らのアイデアで料理していくんです。もちろん見た目の印象は、スタイリング次第でいかようにも変えられるんだけど、僕らのように日々ファッションと向かい合っていると、洋服自体が持つ意味というのが、たまに「うざいな」って感じられるときがあるんですよね。そしてその意味の大半は、今の時代の僕らにとってどうでもいいことだったりするんです。例えば、トレンチコートの袖にはなんでベルトがついているの? とか。あれには水や風を通さないためにギューッと縛るという目的があったけど、いまはそんな風に捉えて着ている人なんかいないでしょう? 同じくトレンチコートのウエストのベルトには“Dカン”が付いているけど、あれはそもそも、ベルトに手榴弾を付けるためのディテールだったりとか。いまも当時の名残りとして残ってはいるけれど、現代の僕らからすると「だから何?」という部分ももちろんありますよね。

——知っていようがいまいが、それを着る上ではあまり問題にはならないし、意味もない。形骸化された知識という感じですね。
三原:そう、知識でしかない。それは持っていて悪いものではないと思うんだけど、そういう知識、いわばデータに単に従っていくようなやり方に、僕はもううんざりしていてね(笑)。例えば僕も、よそのブランドでミリタリーのディテールを見たとき、「ここはステッチを1本忘れてるな」とか、「縫い方が違うな」とか気付いてしまうことがよくあるんです。でもそこを許せなくなっていくと、もはや洋服の善し悪しじゃなくなってきますからね(笑)
——洋服好きの末路……という感じですね(笑)。
三原:洋服好きが行き着く先って、だいたいそこなんですよね(笑)。僕はこの写真集がすごく好きなんですよ(蔵書『American Denim』を手に取って)。アメリカのヒッピーの人たちがリメイクしている洋服がたくさん載ってるんだけど、こういうのを見るとリメイクってやっぱり自由だなと感じます。デニムにペイントしたり刺繍してみたり、そういうのって最初は誰かの模倣から始まるのかもしれません。でもハマっていくと、唯一無二の世界を作っちゃう人も結構いるじゃない? 自分の目で見て触れてっていう手作業の良さって、そこだと思うんですよね。僕にはこんなことできない! って思うようなクリエイティビティが、この写真集にはたくさん溢れているから。


三原さん自身のカスタマイズに対する熱い思いや活動内容を聞いたところで、いま既製品をカスタマイズする意味とは何かを、引き続き語ってもらいました。話は、“時間の使い方”にまで及びます。