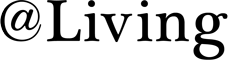緑が芽吹き、景色が色鮮やかに変わっていく季節がやってきました。植物の楽しみ方の定番といえば切り花ですが、今年は、近年じわじわと人気を集めている「枝もの」を飾ってみるのはいかがでしょうか。
農林水産省のデータによると、2011年から2021年の10年間で生花全体の産出額が4%落ちているなか、枝ものは87%も増加。最近では、定期的にお花が自宅に届くサブスクサービスにも、枝ものに特化したものが登場するなど、人気が高まっています。
そこで、ご自身も自宅によく枝ものを飾るというフローリストの前田有紀さんに、枝ものの魅力や、長持ちさせるためのコツ、季節ごとのおすすめの品種などを教えていただきました。
CONTENTS
いま話題の「枝もの」とほかの植物、何が違う?

切り花、鉢植え、観葉植物など、自宅で楽しむ植物にはさまざまな種類があります。そのなかで近年話題の「枝もの」にはどのような特徴があるのでしょうか。
「枝ものとは、お花が咲いたり、葉がついたりした木の枝全般の総称です。切り花と大きく異なるのは、その季節にしか手に入らないところ。切り花の場合、日本ではビニールハウス栽培が盛んなので、冬に夏のお花を手に入れることが可能です。
それに対し枝ものは、実際にその枝が見ごろを迎える季節にしか市場に出回りません。つまり、真夏に桜を飾りたいと思っても手に入れることはできないということです。
いつでも好きなお花を楽しめる切り花ももちろん素敵ですが、楽しめる季節が限られている枝ものには、四季を存分に味わえるという、ほかにはない魅力があります」(フローリスト・前田有紀さん、以下同)
「四季」を感じられ
「長持ちする」のが人気の理由

さまざまな植物があるなかで、どうしていま「枝もの」に人気が集まっているのでしょう。
「一番の理由は、先ほどお伝えした通り、季節を感じられることかと思います。そして、切り花よりも長持ちする点も魅力です。
生花の多くは、買ってきて1週間ほどで枯れてしまいますが、枝ものは長ければ1ヶ月ほど、ものによってはもっと長く楽しめるものもあります。たとえば、ドウダンツツジや馬酔木(アセビ)などは、1ヶ月ほど、その緑を楽しめます。
お花がつぼみの状態で買ってくると、飾っているあいだに少しずつ開花していきます。ひとつのお花が咲き終わっても、また次のつぼみが開いたり、花材によっては葉が生えてきたりすることも。生花よりも格段に長く、かつ、飾りながら変化を楽しめるのも、人気の理由かもしれません」
枝物ならではの花瓶の選び方

いざ枝ものをお家に飾るとなれば、まず必要なのが花器です。花器には、大きさも素材も形もさまざまなタイプがあります。
「枝ものは切り花よりも重さがあるので、土台が軽いと倒れてしまう可能性があります。そうならないために、土台がしっかりしていて安定感のある花瓶を選ぶことが大事。
そう言われると、大きな花瓶を用意しなくちゃと思われるかもしれませんが、丈を短くすれば、生花用の小さな花瓶に入れることもできます。
雪柳(ユキヤナギ)や小手毬(コデマリ)など、春の枝ものは比較的軽いものが多いので、枝によっては小さめの軽い花瓶で対応でき、初心者でも飾りやすいでしょう」

枝ものの花瓶というと、以前は透明でシンプルなものが主でしたが、最近はそれも変わってきているそう。
「最近はカラーリングを楽しむ方が増えているので、さまざまなデザインの花瓶が登場しています。私自身も、花瓶に彩りがあればあるほど、コーディネートをするときのワクワク感が高まると感じています。
たとえば、ピンクの花瓶には、桃や梅、桜といったピンク系の花が咲く枝を入れるととてもかわいく仕上がりますし、反対に、グレーなどのシックな色合いの花瓶には、緑が鮮やかな夏の枝ものを入れるととても爽やか。季節ごとに花瓶を変えるのも、枝ものを飾る楽しみのひとつです」
このひと手間で失敗しらず!
日持ちさせるためのテクニック
切り花よりも長く楽しめる。とはいえ植物なのでもちろん終わりはあります。できるだけ長く飾るためにはどうしたらよいのでしょうか?
「水をこまめに変えるのは基本中の基本。できれば毎日変えてあげましょう。また、飾るときにひと手間かけると日持ちしやすくなるので、今回は桜の枝を使ってその方法をご紹介します。まずはお手入れの道具を揃えましょう」
【用意する道具】

・ハサミ
「鉄製のハサミは、使い込むと味が出て素敵ではありますが、定期的に研ぐなどメンテナンスが必要なので、初心者の方はメンテナンスの手間が少ない樹脂製のものがおすすめです。写真のハサミも樹脂製です。私は、刃が汚れてきたら、『激落ちくん』などのメラミンスポンジで汚れを落としています。この方法なら、家の掃除をするときについでに洗えるのでラクですよ」
・フローリストナイフ
「枝ものには、フローリストナイフが必須。お花屋さんではあまり取り扱っていないので、アウトドアグッズのお店やインターネットなどで探すのがおすすめです」
【お手入れの手順】
1.花瓶に入れたときに水に浸かる部分の木の皮を、フローリストナイフで削ぐようにして取る

「枝ものには、木の皮がついたままの状態で売られているものが多くあります。皮を取って、水を吸いやすくしてあげましょう」
2.根元の部分に、ハサミで縦に切り込みを入れる。枝が太い場合はもう一度ハサミを入れ、切り込みが断面に対し十字になるようにする。

「切り込みを入れることで、給水面が増えるので、枝が水を吸い上げやすくなります。枝ものが水をあまり吸わなくて困っている方も、ぜひやってみてください」
3.水に浸かる位置にある小枝を切り落とす

「小枝をそのままにしておくと、水に浸かっているうちに腐ってしまうので、最初に取ってしまいます。切り落とした枝は、小さな花瓶やジャムの空き瓶などに挿すと、食卓や洗面所などを飾りたいときに重宝しますよ」

4. 水を入れた花瓶に入れて完成

「環境が整っていれば、切り花よりも多く水を吸うので、水の減りが早く、気付くと花瓶が乾いていたなんていうことも。とくに暖房の効いた部屋の場合は、お水をたっぷりあげてくださいね」
生きているからこそ終わりがある。
枯れてしまったらどう片付ける?

長く楽しめるとはいえ、ほとんどの枝ものは、切り花同様にやがては枯れてしまいます。楽しみ終わったらどのように片付けるとよいのでしょうか。
「枝ものは大きいので、地域によっては棄てるのが大変な場合がありますし、棄てるよりもほかの植物の栄養になったほうがいいと思うので、我が家では庭にまいて土に返しています。お庭がなければ、鉢植えの土の上にまいてもいいでしょう。飾るときに削ぎ落とした皮も同じように、土に返しています」

また、枝物のなかには、終わりがなくずっと飾り続けられるものもあるのだとか。
「雲竜柳(ウンリュウヤナギ)や赤目柳(アカメヤナギ)などの柳類、ドラセナなどの葉物系は、水に浸かった部分から根が生えてくることがあります。もしそうなったらすごくラッキー。運が良ければ土に植え替えるとうまく育つこともあります。もちろん、そのまま水の中で育てても構いません」

春夏秋冬を楽しむ!
フローリスト・前田さんの季節別おすすめ品種

四季に恵まれた日本では、季節とともに、見ごろを迎える植物の移り変わりも楽しめます。
「買ってきた枝のつぼみを、『いつ開くかな』と待つのも楽しい時間。とくに春へ向かういまの季節は、少しの温度変化にも反応し、お花が咲くので目が離せません。
今回の記事では、なるべくたくさんのお花が咲いている写真を撮っていただきたいと思ったので、前日の夜に寒いリビングから暖かい寝室へ移動させ、『咲きますように』と願いながら一緒に眠りました。
春は枝ものの種類が豊富になるので、はじめて枝ものをお迎えするのにもピッタリな季節です」
ここからは、季節ごとにおすすめの品種をご紹介します。
早春〜春(2〜5月)……小手毬、雪柳、木蓮(モクレン)、桜、桃、ハナミズキ など

「早春から春に出回る枝ものには、美しい花を咲かせるものが多くあります。外の景色が色づくよりもひと足先にお家に迎え入れれば、ワクワクしながら春の訪れを待つことができます」
夏(6〜8月)……ドウダンツヅジ、馬酔木(アセビ)、スモークツリー など

「夏場は花瓶の水が濁りやすくなるので、長持ちする枝ものを選ぶのがおすすめ。綿のようにモクモクとした風合いで人気のスモークツリーは、名前こそツリーですが、実は夏の枝ものなんです」
秋(9〜12月)……野ばらの実、鈴ばらの実、ツルウメモドキなど

「秋は、赤く色づく実ものがかわいく、色も映えてきれいです。野ばらの実は、秋が深まるにつれ、緑から赤に変化するので、そのグラデーションとともに季節の変化を感じることができます」
冬(12〜2月)……針葉樹、スギ、ヒノキ、もみの木 など

「冬は、クリスマスツリーに使われるようなものや、温もりを感じさせるものがおすすめです。ホリデーシーズン感が出て、寒い冬を温かい気持ちにしてくれます」
季節を問わず気軽に挑戦するなら?

「水を変えたり、メンテナンスを続ける自信がない方は、まずはドライにした状態のものから取り入れてみるのはいかがでしょう。ドライのものであれば季節を問わず手に入れられます。なかでもおすすめはインテリアとしてもよく使われるユーカリとパンパスです。
ドライから始めて、ゆくゆく生花に挑戦するというのもいいでしょう。ちなみにユーカリは丈夫で育てやすく、生花でも1年中流通しています。パンパスの生花は晩夏から秋頃に出回りますよ」
お家時間を豊かにしてくれる枝もののある暮らし
都会や街中で暮らしていると、自然が遠い存在になりがちですが、枝ものを飾れば、家にいながらにしてその季節ならではの自然と触れ合うことができます。
「冒頭でもお伝えしてきたように、枝ものは土で育てるよりも扱いやすく、切り花より長持ち。さらに季節も感じられる。まさにいいことづくめなので、植物のなかでも暮らしに取り入れやすいジャンルだと思います。まだ切り花ほどには知られていないので、ハードルが高く感じるかもしれませんが、一度、お家に迎え入れてみればきっとその虜になると思います。ぜひ、初心者の方にも気軽に取り入れていただきたいです」
自宅にいながらにして、日本の豊かな四季を楽しめる「枝もの」。この春は、ぜひお家に迎えてみてはいかがでしょうか。
Profile

フローリスト・株式会社スードリー代表 / 前田有紀
10年間のテレビ局勤務を経て、2013年イギリスへ留学。見習いガーデナーとして働いた後、都内のフラワーショップで3年の修業を積む。「人の暮らしの中で、花と緑をもっと身近にしたい」という思いから、様々な空間での花のあり方を提案。11年目。2018年、自身のフラワーブランド「gui」を立ち上げ、2021年には実店舗「NUR」をオープン。2025年4月10日に、新店舗「gui flower design」を鎌倉にオープン予定。
HP
Instagram
gui flower design
住所:神奈川県鎌倉市御成町9-42
Tel:0467-33-5838
営業時間:9:00-17:00(プレオープン期間の4月中のみ)
定休日:水・木
取材・文=鈴木まゆ 撮影=鈴木謙介