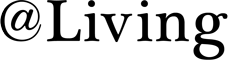自宅でワインを楽しみたい、できれば産地や銘柄にもこだわりたい、ワインを開けて注ぎ、グラスを傾ける仕草もスマートにしたい……。そう思っても、基本はなかなか他人には聞きにくいもの。この連載では、そういったノウハウや、知っておくとグラスを交わす誰かと話が弾むかもしれない知識を、ソムリエを招いて教えていただきます。
「ワインの世界を旅する」と題し、世界各国の産地についてキーワード盛りだくさんで詳しく掘り下げていく、このシリーズは、フランスをはじめとする古くから“ワイン大国”として名を馳せる国から、アメリカなどの“ワイン新興国”まで、さまざまな国と産地を取り上げてきました。今回はいよいよ、日本。寄稿していただくのは引き続き、渋谷にワインレストランを構えるソムリエ、宮地英典さんです。
【関連記事】
第1回 :フランス
第2回:イタリア
第3回:ドイツ
第4回:オーストラリア
第5回:アメリカ
第6回:ニュージーランド
日本ワインを旅する
「日本ワインの歴史は浅い」という話をよく聞きますが、他国に比べて、本当に浅いものなのでしょうか? こと歴史という点では、5世代続く家族経営のワイナリーもありますし、サントリーやメルシャンといった大手メーカーの歴史は100年以上続いています。
日本人のワインとの初めての出会いは、16世紀にさかのぼります。ポルトガルの宣教師が日本に持ち込んだものだったようです。珍重され流通した時代もありましたが、“国内で生産する”という流れにはならず、江戸時代の鎖国政策でそれも一度途絶えました。
そして明治維新が起こり、ヨーロッパを視察した岩倉使節団はワインが産業として重視されていることを知り、新政府の産業振興の一環としてワイン造りを奨励したことが、“日本ワイン”の始まりとなります。日本人として初めてフランスに留学した山梨県の青年2人は、1877年(明治10年)に日本初のワイン会社である大日本山梨葡萄酒会社を設立し、これが現在のメルシャンの起源ともいえる事業に。時を同じくして全国各地にワイン醸造家が生まれ、サントリーも1899年に創業し、ワインの製造販売を始めます。
ですが、ワイン産業が奨励された後も、通常のワインは食卓になかなか受け入れられず、神谷伝兵衛の「蜂ブドー」やサントリーの「赤玉ポートワイン」といった人工甘味果実酒だけが成功を収めました。多くのワイン醸造家は苦しい時代を過ごしたことは想像にかたくありません。
そして明治維新から約100年。1970年の大阪万博をきっかけに幕を開けた高度経済成長の時代に、第一次ワインブームが起こり、1975年に初めて、ワインの消費量は甘味果実酒を上回ります。
ヨーロッパでの現代ワインのスタイルを体系化した原産地呼称制度は1920年代、アメリカやオセアニアが現在のワインのスタイルを確立していったのも戦後の20世紀後半になってからのこと、と考えると、歴史そのものはけっして見劣りするものではないように思えるのです。
それよりも生育期の高温多湿、梅雨や夏から秋にかけての台風といった気候条件と、現在世界中で脚光を浴びる「日本酒」という米文化、ヨーロッパの食文化が根付くのに時間が必要だったことが、ワイン文化を育み、ワイン用ブドウを栽培することに積極的になれなかった、大きな要因だったように思えます。
現在、日本のワイン消費は第7次ワインブームの真っただ中。チリワインなどの低価格帯ワインの家庭消費やバル、レストランの多様化など複合的な要因がありますが、そのひとつに「日本ワインブーム」もあるとされています。今では北は北海道、南は九州まで、幅広い地域でさまざまなスタイルの日本ワインが造られるようになり、目を見張るような素晴らしい品質のワインにも出会えるようになってきました。
100年以上の時間が必要だったとはいえ、日本ほど世界中の多様なワインが消費されている国はなく、また美食という観点からも、日本ほどレストランが高いレベルでしのぎを削る国はありません。そのなかで日本ワインが、国内のみならず海外でも広く知られる日は、もうすぐそこに迫っているように思えます。日本ワインの個性やスタイルといったものが確立されるのは、近い将来のことなのです。
1. 山梨県
2. 長野県
3. 栃木県足利と北海道
4. 山形県
5. 新潟県
1. 山梨県
− 日本ワインらしさを期待される甲州種の可能性 −
山梨県は、日本のワイン生産の発祥の地であり、山梨大学と県の産業技術センターに属する“ワインセンター”という研究機関をそなえる、歴史的にも技術的にも日本ワインの中心的な生産地です。メルシャンやサントリー、マンズ、サッポロなど大手メーカーの拠点もありますが、写真の「中央葡萄酒」のような家族経営のワイナリーにも注目が集まっています。
日本ワインのオリジナリティという話で、必ず名前が挙がるブドウ品種が「甲州」種です。山梨県勝沼で古くから栽培されてきた甲州種は、DNA研究によって3/4がヴィティス・ヴィニフェラ系であることがわかり、甲州種ワインの成功はすなわち日本固有のワインの成功につながると、これまでさまざまな工夫が重ねられてきた品種なのですが、元来生食用に栽培されてきた甲州種は糖度が上がりづらく、ワイン用のブドウには不適な面もあったのです。ワイン用ブドウは少なくとも20度、ボリュームのある味わいを得るには24度ほどの糖度が必要と言われていますが、甲州は通常だと16~18度ほどの糖度にしか上がりません。そこで中央葡萄酒の三澤茂計氏は、従来の棚仕立てから、海外で主流である枝を縦に這わせる垣根仕立てを採用し、ワイン用ブドウに必要な糖度を持った凝縮した果実を栽培しようと試みます。ところが1992年に初めて採用した際には、樹勢の強い性質から結実すらしなかったといい、挑戦は失敗に終わります。そして現在の醸造長である三澤彩奈氏は垣根仕立てに加え、高畝式というブドウ樹になるべく水分を吸わせない方式を採用、2012年に初めて糖度20度を超え、2013年には25度の果実が生まれるようになりました。
この年醸造した「キュベ三澤明野甲州2013」は世界最大のワインコンクールであるデキャンタ・ワールド・ワイン・アワードで、日本ワイン初の金賞を獲得します。当時、日本経済新聞に掲載された金賞獲得の記事を読んだ際、日本ワインの夜明けを感じるような感慨、わがことのようにうれしく思ったことを、昨日のことのように思い起こせます。三澤茂計氏にとっては20年以上、代々続く中央葡萄酒、山梨のワイン、日本ワインにとっては100年に及ぶ挑戦のひとつの結実だったと思えるのです。
こと甲州種によるワインは、日本ワインのひとつの方向性を示しました。そしてそれは現在進行形のもので、より深くより明確に日本ワインのオリジナリティを表現していく期待が、甲州種には集まっているのです。

中央葡萄酒「グレイス甲州 2019」
オープン価格