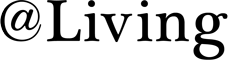「僕が本格的に工房で硯作りを始めたのは、幼い頃から自分を可愛がってくれた祖父が亡くなってからのことでした。ちょうど20歳くらいの頃だったのですが、その時父に丁稚奉公に行きたいと申し出たところ、父は“行く必要はない”と言ったんです。というのも、現在の日本の硯作りは、日本独自に発展した書道文化の形式に則っている部分が大きい。でも、この宝研堂で僕の祖父や父が脈々と受け継いできたのは、本来中国で生まれた硯の本質でした」

「例えば中国で作られている硯には、それが“名硯(めいけん)”と呼ばれるような優れた硯であっても、作者の名前が彫られていることは基本的にありません。古代中国において硯は権威の象徴でしたから、そこに刻むのは硯の作者ではなく、持ち主の名だったんですね。さらに、中国には1000年以上も使い続けられているような古硯(こけん)も数多く存在しますが、それらの硯に必ず共通しているのが、石の美しさが最大限に生かされているということ。つまり石より前に出てしまうような作家性を重視した造形の追究より、石を生かした結果の伝統的造形こそが製硯の中心にあるということなんです」

良質な石を見抜き、その石紋の美しさと墨のすりやすさを同時に引き出し、持ち主がいつまでも手に触れていたい、文字を書き続けたいと思ってくれるような硯を作ること。これが、採石から仕上げまですべてを担う、製硯師の仕事であると青栁さん。
「同時にそれは、硯の源流である中国でいまだ守られている考え方と同じです。その源流に習って硯製作を行っている僕らのやり方を“青栁派”と自称しているんです」

地球が1億5000万年かけて作った石で
僕らは仕事をさせてもらっている
硯の製作や修復のオーダーを受けることはもちろん、夏目漱石遺品の硯を修復で再現したり、日本では初めてとなる北海道での硯石の採石、大学で硯文化について授業を行ったりなど、とにかく仕事の内容が多岐に渡っていることでも知られる青栁さん。16歳から祖父と父に師事し、40歳を迎えたこの春までひたすら硯と向き合ってきた中で、活動のフィールドは次第に広がっていきました。
「(工房内の戸棚を指差して)そこにふたつ並んでいる石のうち、右にあるのが江西省で採れる歙州硯(きゅうじゅうけん)という石です。そして左にあるのが、広東省で生まれた端渓硯(たんけいけん)という石。いずれも、地球上で存在している硯の素材の中で、これらより優れている石は今のところないとされている石なんです。しかも文献上では、1500年前の晩唐の時代にどちらも採掘され、硯になっているんですよね。硯の本質、石の活かし方を学ぼうと思ったら、これらの名硯が生まれた文化や時代背景を知るしかない。だから僕は、30代の前半くらいから採石地にも積極的に足を運ぶようになりました」

そこであらためて感じるようになったのは“地球”だったと、青栁さんは自著「硯の中の地球を歩く」(左右社)に書いています。
「1億5000年かけて地球が作った石で、僕らは硯を作らせてもらっている。天然の素材だからこそ、己の技術でなんとかしてやろうってムキになるほど、なんともならないのが硯なんです(笑)」
硯石やそれを研ぐための砥石は、今や青栁さんにとってダイヤモンドよりも価値のあるもの。中国の険しい山へ何日もかけて調査に出向いたり、時には石を見て触るだけなく石粉を舌で舐めて(!)みたり、良質な硯作りを追求していく過程で、石とのお付き合いもより濃密なものになっていったようです。
「地球が生んだ貴重な資源を使っているからこそ、1回使って壊れるようなものを作っちゃいけない。そう思うようになりました。僕は自分で鉱脈を探すようになってからようやく、端渓や歙州がなぜ100万円なんて値段になるのかがわかるようになったんです。1000年使い続けられるものを作っていく。それも青栁派の考え方のひとつです」

硯の製作技術や石を学び、追求してきた青栁さんは、この春ひとつの面白い試みを実現させました。